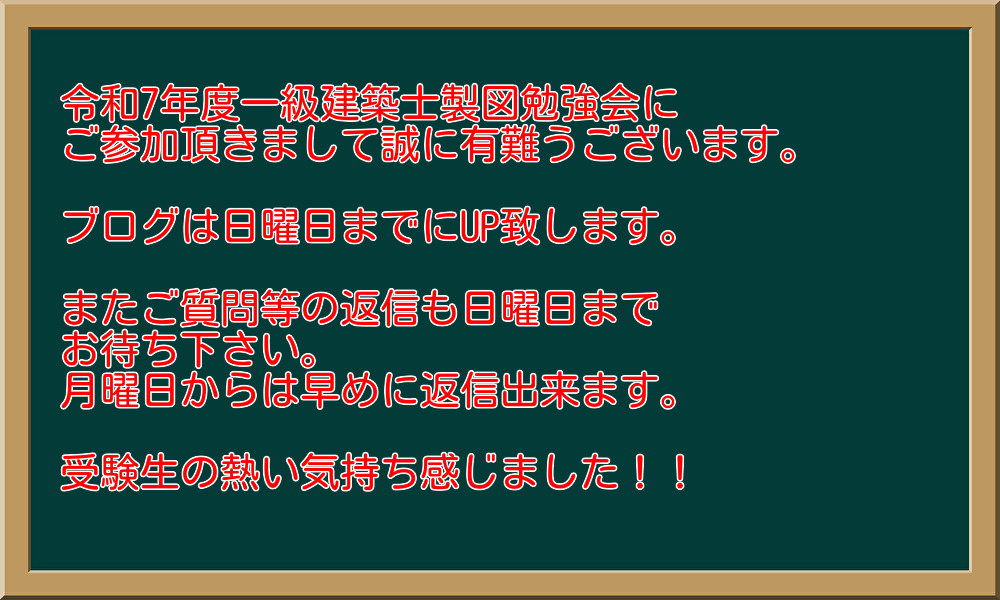本日はエスキスの考え方(一級建築士製図試験攻略テキスト20ページ~21ページ)についてお話したいと思います。
テキストが手元にない受験生は雰囲気だけ感じて頂ければ嬉しく思います。
適宜=適当(施主の要望はお任せ)設計者の腕の見せ所♪
20~21ページ
適宜=適当で良いと思います。
実務でもお客様と打ち合わせ中に『お任せします』と言われる機会が多々あると思います。
各部屋の主要部分以外(W/C等)のクロスは色合いだけ聞いて、こちらで決めるのではないでしょうか?
適宜=適当と言っても、本当に適当にすると後でクレームに繋がる恐れがあるため、必要最低限の基準は満たす必要があります。W/Cの壁紙をお任せと言われても、真っ赤なクロスは選択しないと思います。
一級建築士製図試験も同じです。新試験になり適宜の要求が増える事で自由度が増しました。
適宜=適当=お任せ=常識の範囲内で計画する事が求められます。
試験元が適当力を求めている以上、合格する為には受験生の皆様も適当力をUPする必要があります。
適宜の要求室の計画は、一見難しように思われますが、大丈夫です!心配しないで下さい。
建築には多機能便所等、ある程度規格が決まっています。
そのため、適宜要求は暗記で対応すれば大丈夫です。
※適宜の要求室等の面積は、毎年少しずつ変わっている&資格学校によって違うため、その都度アップデートが必要です。
資格学校ではオスメイト機能付き多目的トイレは2m×3mと指導されていると思いますが、最近は2m×2mを下回るコンパクト設計の多機能トイレも珍しくないので、資格学校の指導が最先端という訳ではないです。
僕が受験生だった頃は、更衣室の最小面積は最低2m×5m=10㎡と習ったのですが、今は6㎡で教えている所もあります。
まぁ!それが適宜の怖い所です。限界に挑戦みたいな・・・。
基本の適宜の考え方!
第1案目は最小の面積で計画する事が基本の考え方になります。
僕の場合は、更衣室であれば第1案目は最低10㎡で考えます。(理想は15㎡)
※9㎡だと減点だったため、減点されない最小面積で計画。今では6㎡になっていますが(T_T)
適宜の要求室を最小の面積で計画すると、プラン終了後に最大床面積まで余裕がある場合が多いため、後から面積を増やします。(10㎡→15㎡)間口2.5mで12.5㎡、間口3mで15㎡。
最小面積でスタートするメリットは、仮に最大床面積に余裕がない場合、無理に面積を増やさなくても条件違反(減点対象)にはならない事です。すでに最小の面積は確保しているため。
しかし、逆に要求面積にゆとりを持たせて計画すると、最大床面積オーバーの場合再度面積を調整する必要性があります。
1分1秒を削り出したい一級建築士製図試験は手戻りをなるべく避けたいため、第1案目は最小面積でエスキスする事が大事です。
設備機械室の大きさも必要な容量を計算せずに、㎡数は導き出せないため、迷ったら1コマ確保しておけば良いのではないでしょうか?
全体の2%!こんな感じで決める事が出来るのなら、建築設備士や設備一級の人は必要ないですね。
用語の定義!日本語は難しい(T_T)
日照に配慮する=採光に配慮する!ではありません。
- 日照に配慮する 優先順位は南→東→西→北
- 採光に配慮する 外壁面(光庭等に面する)に計画する。
一体的に利用する=動線に配慮する!ではありません。
- 一体的に利用する 隣接させる。
- 動線に配慮する 近接させる。
こんな感じで微妙なニュアンスの違いを感じ取る事が重要です。
動線も横の動線と縦の動線があります。要求室の配置によっては縦動線の方が近接する事があります。
※2階の隅から隅に移動するより、EVで1階→2階に上がる方が近い場合もある。
まとめ
重要なパートなので、2ページだけの説明になりました。
この辺りは暗記で対応出来る事が多いため、エスキスを攻略する上で必要な知識となります。